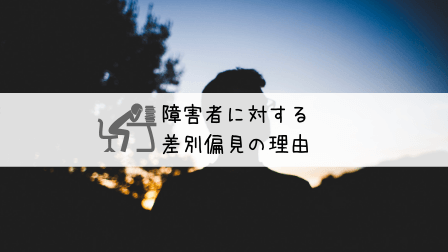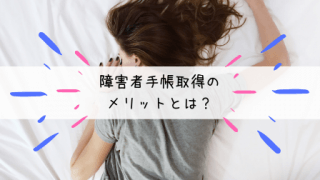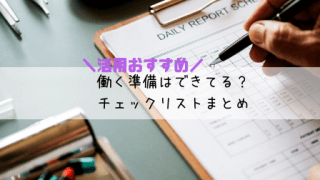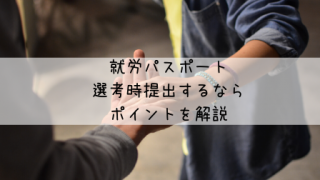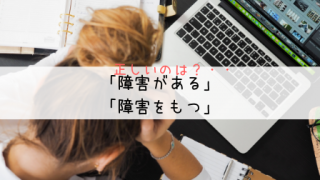現役就労移行支援員のよしころろです。事業所や公式のサイトではお伝えできない本音やぶっちゃけた話等知らないと損する情報をブログで発信しています。
障害者差別はいけない。それはみなさんご存知のことだと思います。
ただ、現状差別はまだまだあります。ただ差別はしたくなくてもおこるものなんです。
差別や偏見の理由についてまとめました。みなさんあてはまるかも!
障害者差別や偏見が起こる理由はひとつじゃない
差別や偏見がなくならない理由はいくつもあります。
障害者差別はなぜおこるのか、その内容を知ると共感できるところがあるのでは?と思います。
障害者差別の原因は「知らないもの」への恐怖
アメリカの思想家であるエマーソンは 『恐怖はつねに無知から生じる』と言いました。
経験がないことや分からない事に恐怖を感じるのは、知らないなりにあれこれと想像してしまうからかもしれません。
もし精神障害について詳しく知らず、隣の家に精神障害をもっている方が住んでいることを知ったら、ちょっとビビりませんか?
しかし、それは精神障害が実際はどんな病気なのか知らないからであり、 実際にその病気の方に会ったり、障害について知ることによってその恐怖は薄れます。
そもそも、そういった障害をもつ方に関する恐怖は障害者の方と触れ合う機会がない社会に問題があると思っています。今じゃ 16人に1人は障害をもっていると言われているのに、生活の中であまり出会わないと思いませんか?
知る機会、きっかけがないだからこそ恐怖を感じてしまうのはしかたないかもしれません。ただ、悪意をもって関わるのはだめです。
必要以上に恐れる必要はなく知らないのであれば知りましょう。学びましょう!
障害者差別の原因は「障害者は家の恥」という歴史的な背景
古代世ヨーロッパでは、障害者は迷信、迫害、排除の対象であったと言われています。障害をもった子供が生まれるとサタン(魔王)の申し子と見なされていたとか。
日本でも、中国から宗教が日本に広まった頃「因果応報」という考え方が広まりました。
因果応報は悪い原因を作れば、必ず悪い結果がもたらされる、という理念です。悪いことが起こらないようにと戒めの意味で使われるのなら問題は ありません。
しかし、表れている事柄から逆に、結果からどんなにか悪い事をしたに違いない、という評価を与えることになりました。
障害者が生まれたら、障害者を先祖の罪であるという否定的な価値観がうまれ、「家の恥」をそとにさらしてはならない風土をうみました。
年齢が高くなるにつれて障害について偏見があるのは歴史的な背景があるからだと思います。
障害者差別の原因は社会の発展の影響から
社会モデルの代表的な論者、 V.フィンケルシュタインは、近代産業社会の発展に伴ってこういった差別社会が創造されてきたと主張しています。
簡単にまとめると、小規模な生産が個人の家で行われていたような時代では、障害がありながらも家庭内、身内で本人ができることで家の手伝いをすることができ、障害をもっている方なりの役割がありました。
しかし社会が発展していくにつれて工場労働などが中心となり、個人での生産活動はなくなり障害を持っていた方の役割は失われます。
工場での労働形態が基本となり工場の生産ペースについていけない者は労働現場から排除されるようになりました。
そこで障害をもった人が働けず家にいるような環境が生まれて、「働かざる者食うべからず」なんて言われるようになりました。
今は、障害の度合いや本人の希望により、いろいろな働き方が仕組化されています。
通常の労働生産についていけない方も本人ができる範囲で社会参加ができます。
今後は障害を強みに働くことができます。社会が発展する中で福祉の制度も発展していったことがよくわかります。
障害者差別の原因は少数派であることから
今16人に1人は障害をもっていると言われていますが、逆に16人のうち15人は障害をもっていません。
障害を持っている方は、持ってない人と比較すると少数派です。
国の制度や政治は、国民の声によって整備されていますがより多くの人の声に左右されます。
そうなるとやっぱり少数派の意見は反映されにくいです。
誰にでも生活しやすい環境や仕組みは難しく、少数派であることは人権を迫害されやすい人たちと言えます。
私たちにとってよいことが、他の人にとってもよいことであるとは限らないのです。
障害者差別の原因は教育現場での先生のスキル不足
初めて障害をもっている人、「何かが違う」人と出会う、関わる、見るみたいな機会があるのが小学生の頃だと思います。
なかには、障害が発覚しておらず授業中どうしてもついていけない子どもがでてきたときに、「ただ怒る」、できない人を排除するような指導をせずじゃあどうしたらできるようになるのか?という視点で本人へのかかわって頂き、その周りに対いて偏見が起こらないようなフォローをしてほしい。
社会にはいろんな障害を持った人がいること、それは自分もいつかそうなってしまう可能性があること、それでも社会では働いていける仕組みがあることを伝えてほしい。
ただ、学校の先生は社会人の経験がなく考えが偏っている場合が多く、幅広い障害に対しても知らない人が多くいます。
学校現場で適切な指導、サポートの方法を知らない先生がいるからこそ差別偏見が進んでしまうことがあります。
障害者差別の原因は優越感に浸りたい思いから
人間だれしもが「優位にたちたい」「価値がある人間でありたい」 と思うものです。
しかし、だからといってそれを満たすために 何らかの少数派をさげすんでしまう(自分より能力・人格の劣るもの、価値の低いものとみなすこと) ことがあります。
そもそも、なぜそうやって人と比べて自分に満足してしまうかというと、 自分を知るには比較する対象が必要になるからです。
そうやって他人と自分を比較し、そこで他人が自分より劣って いたなら自分には価値があると考えます。
相手を軽んじることで、自分のプライドを保とうとする、 人間のかなしい自己防衛本能だといわれてます。
これは、本能的なもので、自分でコントロールできないものです。
自分の中だけでその優越感に浸るのはまだよいです。
ただ公に比較した対象をさけすんでしまうのは幼稚です。
「障害者よりまし」とか「障害者になったら不幸」そんな言葉を言ってしまう人がいます。
人の価値や幸せかどうかなんて自分が判断するものではありません。
どのような環境でも幸せかどうか決めるのは 自分自身だからです。
人と比べることで自分が幸せだと思いこむことは、人のいいところをみると自分が劣っているように見えてしまうことになるので、自分も苦しめてしまいます。
人はそれぞれが本当に違っていて、求められているもの、自分が目指すべきものが、本当にひとりひとりで異なっているし、一人ひとりの役割が違います。
結局自分を幸せにするのも不幸にするのも自分でしかないのです。
差別はだめ!しかし偏ることは悪いことばかりじゃない
偏見とはかたよったものの見方のことをいいます。
ある対象,人,集団などに対して,十分な根拠なしにもたれる,かたよった判断,意見などをさす。
悪い言葉として使われることが多いですが、偏見はリスクを回避する合理的な考え方でもあります。
例えば企業は高卒の学生より東大生を積極的に採用したい!
それは、高卒のが学生より東大生の方が優れている場合が多いからです。東大生を採用した方が、勉学に励んできた年数が長く受験勉強への努力などを背景に失敗が少なくよく幅広い知識から活躍してくれるとメリットを感じます。
あなたが社長だったらそう思いませんか?
今、テレビでは犯罪を犯した人が「精神薄弱だった」など報道することがあります。
そういった影響もあり、もしかしたら危険な人かもしれないと思うのは合理的な判断でもあると思うのです。
ただ、決めつけてしまうのはいけませんし必要以上に恐れる必要もありません。
差別してしまわないように気を付けましょう。
まとめ
私なりに調べて障害者差別や偏見の理由をまとめました。
差別や偏見っていけないことだとわかっていても、無意識で上記の理由から悪気がなくても差別や偏見をしてしまう可能性があることを伝えたかったです。
そもそも私が強烈に障害をもっている兄弟に対して偏見や思いっきり差別をしていたと思います。
自分自身差別をしているものの、家族でいるときの周りからの変な目線で簡単に傷つき、障害をもっている兄弟のことを悪く言う人に怒りを覚え心がぐちゃぐちゃだったころがあります。
偏見や差別は受け取りて側の問題でもあります。
思春期の私は異様に周りの目線を悪い方に捉えていたなと振り返って思います。
差別する人はしますし、悪気がない人もいます。
歳をとってやっとちょっとのことで動揺はしなくなりました。
決しましたか?
障害者差別がなくならない理由はなんとなくでもわかりましたか?